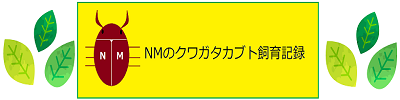
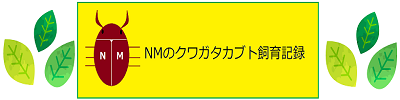





カブトムシ・クワガタの産卵方法はそれぞれの種類によって異なる場合があります。
例えばタランドゥスとレギウスはほぼ同じ種類のクワガタなので、産卵方法は同じですが、タランドゥス・レギウスとブルマイスターでは異なってきます。
このように、種類によって異なる産卵方法についてご説明させていただきます。
↓↓画像をタップ(クリック)すると詳細をご覧になれます。↓↓

タランドゥスは菌糸ビン飼育で幼虫が育ちます。この菌糸ビンはオオヒラタケとカワラタケが存在しますが、タランドゥスはカワラタケ菌糸を用いて飼育します。
メスは直接菌糸ビンに産卵するか、もしくはレイシ材と呼ばれる材木に産卵します。菌糸ビンを用いた産卵をさせる場合は、ある程度劣化させた菌糸ビンを使わないと産んでくれない場合が多いです。

菌糸ビンにメスが潜りやすいように穴を空けます。
オスメスをしばらく同居させた後、メスを取り出して菌糸ビンに投入する方法もよいのですが、交尾に失敗している事もあり産んでくれない場合があります。(この場合は菌糸ビンに潜らずケース内でウロウロしている)
一方でオスメスを同居させている飼育ケースの中に菌糸ビンを置いておく事で、メスが自ら菌糸ビンの中に潜っていきますから効率がよいです。

この方法は、同居しているオスにメスが傷つけられる可能性がありリスクが高いですが、基本的にオスはメスに対して紳士的ですから大丈夫だと思います。
私はこの方法で一度も「事故」が起きた事がありませんし、効率よく産卵させる事ができると言えます。
メスが菌糸ビンに潜って産卵している場合、1カ月近く出てこなくなりますので、オスがメスの産卵を邪魔しないようにメスが潜っている菌糸ビンを取り出して個別管理しています。

レギウスはタランドゥスの亜種なので、基本的にタランドゥスと同じ方法であるカワラタケ菌糸で幼虫飼育を行います。
また、レギウスのメスもカワラタケ菌糸ビンに直接産卵するか、レイシ材に産卵します。
レギウスもタランドゥスと同じ方法(オスメスを同居させたケース内に穴を空けた菌糸ビンを投入)を行っています。
交尾を終えたメスは自ら菌糸ビンに潜っていき産卵を開始しますので、数日潜ったまま出てこない場合は産卵していると判断し、個別管理を行っています。
飼育を行っていて個人的に思う事はレギウスはタランドゥスと比べて産卵しない傾向があるような気がします。
ある程度劣化した菌糸ビンに産卵してくれますが、レギウスの場合はレイシ材を用いる事が多いです。
よく産卵してくれるメスと産卵してくれないメスなど、個体差がありますので、複数のペアで産卵セットを組んでいます。

ブルマイスターは結論から申し上げますと個人的には難易度が高い種類のクワガタだと思います。ブルマイスターは高価なクワガタで、過去ペアを購入しましたが繁殖に失敗したので次世代に繋げる事ができませんでした。
ブルマイスターはレギウス・タランドゥスと異なり、メスは発酵マットに直接卵を産み付けます。幼虫も発酵マットを食べて成長しますが、幼虫は体質が弱い印象があります。

孵化した幼虫はボトルで個別管理を行い飼育するのが基本ですが、餌交換の時に全て新しいマットに交換すると死亡してしまう確率が高いです。
餌交換をする時は、今までの古いマットを幼虫の周りに残しておく事がポイントです。私はこのことを知らずに全て新しいマットに交換してしまい、幼虫を全滅させてしまいました。
繁殖に失敗し次世代を残す事ができなかったため、今は飼育停止中ですが、余裕ができたらまた再挑戦したいクワガタです。

ヘラクレスの幼虫は発酵マットを食べて成長します。メスは発酵マットに直接卵を産み付けます。ヘラクレスのメスはよく卵を産んでくれますし、繁殖は比較的容易に行う事ができる外国産カブトだと言えます。
ただ、幼虫成虫共に体質が弱い印象を持ちます。幼虫も途中で死亡する事が多く、成虫も羽化したばかりの個体は無理に触ると死亡してしまう可能性が高いですから取り扱いには注意が必要です。

ヘラクレスのオスとメスを同居させておくとメスは勝手に卵を産んでくれる印象があります。オスもメスを攻撃して傷つける事は滅多にないと思いますので(過去に事故が一度もない)安全面に関しては比較的安心できるカブトムシです。

ヘラクレスの幼虫はかなり大型化しますから、スペースの確保に問題点があります。比較的大きなケースで個別管理するか、大きな衣装ケースに10匹~15匹程度多頭飼育する必要があります。

ネプチューンオオカブトはヘラクレスと同じく、メスは発酵マットに直接卵を産み付けます。
また、幼虫も発酵マットを食べて成長しますので、発酵マットを敷いたケースにオスメスを同居させる事で産卵させる事が可能です。
ただ、ネプチューンは温度管理がヘラクレスと比べると若干低温での飼育が必要です。(18度~20度あたりが適温)過去にヘラクレスと同じ温度で管理したところ繁殖に失敗しています。
そのため現在飼育は停止していますが、余裕ができたらまた再挑戦したい外国産カブト虫です。